寝不足の毎日をなんとかしたい ー
現在3歳の娘が0歳だった頃、生後10ヶ月まで毎日1~2時間に1回ほど起きてくるという睡眠サイクルでした😇😇
(毎日寝不足過ぎておもちゃを冷蔵庫に入れたりしてました(笑))
そんな経験から、2人目は生まれてすぐネントレするぞ~と意気込んでおりました。
そして間もなく生後2ヶ月になる息子が、夜間は自分で入眠できるようになり、4~6時間ほどまとまって寝てくれています。
(ほんっとうに助かる😭)
この記事では、我が家で試して効果を感じた「セルフねんねの5つのコツ」をご紹介します!
寝かしつけ卒業!2ヶ月でセルフねんねをする秘訣5つ
産後すぐから、ゆるりと”ねんねトレーニング”を続けていた結果、生後2ヶ月になる今では夜の授乳後に自分で入眠をするようになりました。
そんな我が家で取り入れたねんね上手になるための5つのコツをご紹介します!
|1. ねんねの環境を整える
- 明るさ
- 寝かしつけ時には部屋の電気を消す(我が家ではリビングにベビーベッドを設置していて、隣の寝室では上の子が電気をつけて元気に遊んでいることも。ドアを開けているので多少の光や音は入ってきます。)
- 遮光カーテンを使い、明け方の光が差し込まないように調整
- 夜間授乳中は授乳ライトのみを使用し、強い光の刺激がないように注意
- 温度/湿度
- 大人が過ごしやすいと思う温度に調節(2025年6~7月現在で26度くらいの冷房)
- 湿度は気にしていませんが、夜間のみ加湿器はON
- 音
- 最初の寝かしつけの19~20時頃は上の子が起きているため、どうしても足音や声が聞こえる環境
- 1~3時の夜中の授乳のタイミングでは無音
- ベッド環境
- ベビーベッドのマットの上にバスタオルを1枚、枕代わりにフェイスタオルを1回折りたたんで敷く
|2. 昼夜の区別をつける
- 朝の習慣
- 7時~7時半の間に家族全員起床
- カーテンを開けて光を入れる
- 部屋の電気もすべてON!
- この時点で起きていたら「おはよう~」と声をかける
- この時点で寝ていたら起きるまで家事などをする
- 日中は寝ていても気にせず家事をする
- 夜の習慣
- 19時頃にはベビーベッドのあるリビングの電気を消す
- この時、隣の寝室は明るく、光が差し込む状態
- この時間はまだ上の子が元気に大きな声で遊んでいる
- 20時半には寝室も消灯し、家中が真っ暗な状態を作る
- この時間には上の子も就寝のためほぼ無音の状態
- 19時頃にはベビーベッドのあるリビングの電気を消す
このように、朝と夜で光や音の調節をして、”朝は明るくて音がある、夜は暗くて無音である”ということをちょっとずつ知ってもらえるように毎日続けていました。
|3. 日中はゆるくネントレをする
1人目の時は泣いたらすぐに抱っこ、寝ても泣くのが怖くてずっと抱っこをしていました。でも、情報を集めるうちに、「自分で入眠する習慣」の大切さに気付き、2人目では意識的に取り組んでいます。
赤ちゃんが泣く
↓
2~3分見守る
↓
2~3分抱っこ→ベッドに置く
↓
また赤ちゃんが泣く
↓
2~3分見守る
↓
2~3分抱っこ→ベッドに置く
↓
また赤ちゃんが泣く
↓
寝られるまで抱っこ
↓
寝たらベッドに置く
やっているのはこれだけです!
ポイントは、“眠い時にはベッドに横になって寝るもの”ということを理解してもらうこと。そのため、泣いていても2~3分は見守るようにしています。
実際に続けていたら、自分で泣き止んで眠ることが増えました!
上の子がいるので、10分ほど放置せざるを得ないようなことも日常茶飯事のため、「諦めて寝る」みたいなパターンも。(申し訳ない気持ちもあり…ありがたいです😭)
|4. 授乳後はすぐにベッドに置く

授乳するとそのまま寝ちゃうことが多いけど…授乳クッションの上で寝かせてていいのかな~?起きてほしくないしな~!
1人目が0歳の頃は、とにかく起きてほしくなくて、授乳して寝た後にはそのまま授乳クッションの上に置いていました👀
でも!
3年前の私に言いたい。
「授乳が終わったらベッドに置いて!!!!!」
赤ちゃんは、授乳という安心した環境で寝ると、眠りが浅くなった瞬間におっぱいやミルクがないことに気が付いて泣く。(と1人目の時に悟りました)
「あなたはベッドに背中をつけて自分で寝るんだよ~~」
ということを刷り込むことを大切にしていました☺
|5. 授乳での寝かしつけは最終手段に取っておく
授乳は最強の寝かしつけツール。
だからこそ、”最後の切り札”として使うようにしています。
大切なのは、
“最小限の手助けでねんねができるようになること”
かなと思います!!
なので、泣いていると辛いし、心もすり減ってくるけど、なんとか授乳以外の方法で寝られないか格闘をしてみる時間をぜひ作ってみてください!
- 泣いている時の対応ステップ
- オムツ替え
- トントンしてみる
- 座りながら抱っこ
- 立ちながら抱っこ
- 抱っこして揺れる
これでも寝ない&授乳間隔が2時間半以上あいている場合には授乳をしています👀
体重が順調に増加している場合、きっと哺乳量は足りているという(自己判断ですが)推測のもと、授乳後1時間とかで泣いている場合はきっと眠いんだ、眠いに違いない!と言い聞かせて授乳よりもネントレを優先しています。
以上が我が家で取り入れているねんね上手になるための習慣やコツでした!
私自身、1人目の時のねんね事情に本当に苦しんだので、同じように苦しんでいる方や、苦しみたくなくて情報を集めている方にとって少しでもお役に立てると幸いです❁
1人目のねんねの大変さをつづった記事はこちらです!
良ければ合わせてご覧ください!
※ねんねに特化した記事ではありませんが、寝ない様子も具体的に記載しています。
生後すぐから現在までのねんねの変化
生後2ヶ月となった息子は、今でこそ夜間は自分で寝てくれるようになりましたが、産後すぐからセルフねんねができたわけではなく、入院中や退院後すぐには夜間に寝られずに苦労をした日々もありました。
そんな息子のねんねの変化の様子を画像にまとめてみました!

生後間もない頃はもちろん、生まれながらにセルフねんねができるはずもなく、耐え時という感じでした。
生後1ヶ月頃には稀に、気が付いたら「あれ!寝てる!」みたいなことがあって希望の光が見えた瞬間があったのを覚えています。
生後1ヶ月半もすると夜間の寝かしつけがだいぶ楽になってきて、寝られない日の方が珍しい!と思うようになりました。
そして生後2ヶ月になる今、夜の寝かしつけは最後の授乳を終えてベッドに置いたら、いつの間にか自分で寝ています。
【おまけ】参考にしていた情報元
今までお伝えしたネントレの方法や、ねんねの環境の整え方は私が編み出したものではなく、”ねんねママ”さんのyoutube動画を参考にさせていただきました。
本記事には記載しきれなかった、ねんねに関する情報を多数発信していらっしゃる、気になる方はぜひ覗きに行ってみてくださいね❁
最後に、私の「ねんね」と「寝不足」についての想いだけつらつらと書いて終わろうと思います。
繰り返しお伝えしているように、上の子は生後10ヶ月まで毎晩1~2時間おきに起きては泣き、授乳して寝かしつけ、を繰り返していました。
育休中だったので仕事はなかったものの、子供と丸1日をどうにかして過ごさないといけない日々に、あの寝不足は心身ともにきつかったです。
後から考えれば考えるほど、
"泣いたらすぐ抱っこして、寝ても抱っこし続けていたこと"
"寝かしつけはいつも授乳でしていて、寝ても授乳クッションに置き続けたこと"
この2つの習慣が上の子のセルフねんねを習得する機会を奪ってしまっていたんだろうな~と思います。
あの頃はとにかく、「泣くのが怖い」「1分でも長く静かで平和な時間がほしい」と思ってしまい、寝ても置けないという状態でした。
今、あの頃の私に言いたいのは
寝たら置け!!!
泣くのを恐れるな!!!
です。(笑)
この記事を読んでいる寝不足やねんね事情に悩むすべての方に、1日でも早い寝不足からの解放を願っています!!!!
自分らしく、まいにち育児をもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。
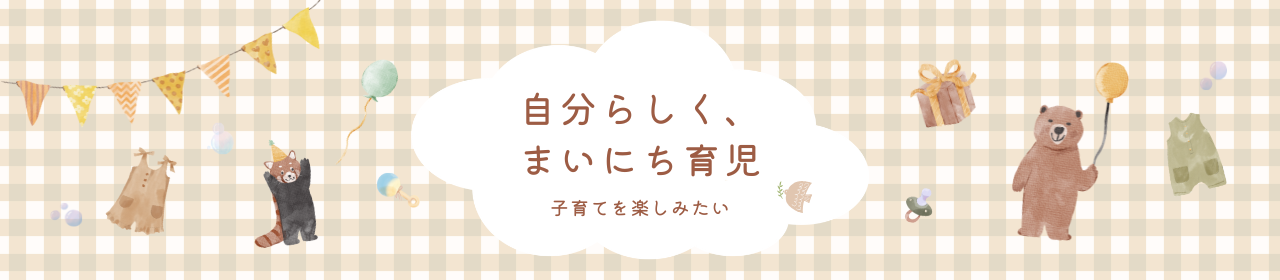
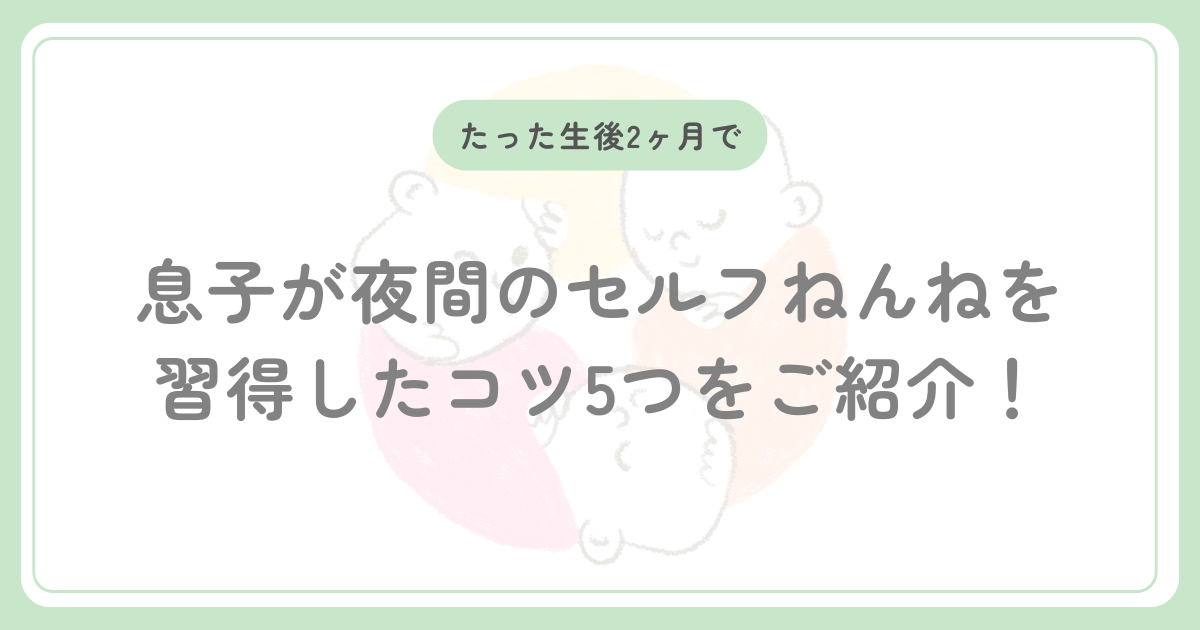
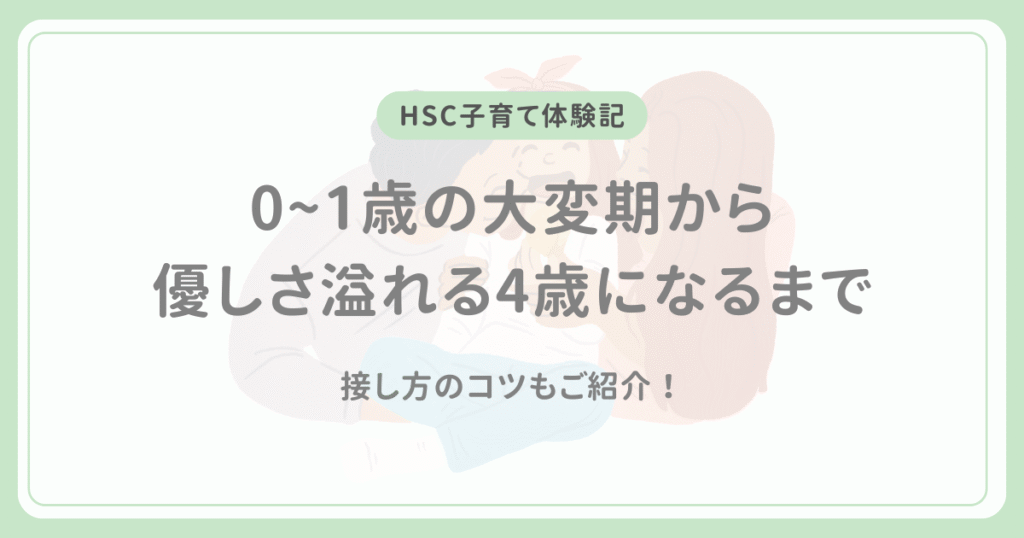
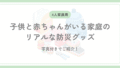
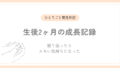
コメント